まったく信じられないのだけど、2021年が半分過ぎ去りました。光の速さで。
悔しいので、年初から半年の間で読んだ書籍を晒しておきます。読了したのは4冊。目標には届かないペースでした。
ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか
PayPal創業者で知られる起業家にして、Facebookほか、テクノロジー界隈のベンチャー企業に投資する投資家ピーター・ティールによる、彼の母校スタンフォード大学での起業講義録。
日本語版序文は2019年に惜しくも亡くなられた瀧本哲史氏。亡くなられたタイミングで、これはもういつかではなく今読まなければ、と思いつつも1年半は放置してました。
2021年の個人的なテーマのひとつに「競争を避け、独占する」というものがあるのですが、これは本書の教えをそのまま拝借したものだったりします。
我々サラリーマンは、多かれ少なかれ競争の中に身を置くのだけど、競争は疲弊するだけ、それもよりもプレイヤーがほとんどあるいはまったくいない市場でナンバーワンになった方が良い、という指摘は、個人の戦略としても非常に参考になります。
起業論のほか、
案件ごとに働く人間が入れ替わり、単なる仕事だけの関係しか持てない職場は、冷たいなんてものじゃない。それに、合理的でもない。時間はいちばん大切な資産なのに、ずっと一緒にいたいと思えない人たちのためにそれを使うのはおかしい。
ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか
など、組織のマネージャーやリーダーにも、一度は目を通していただきたい内容でした。
HARD THINGS 答えがない難問と困難にきみはどう立ち向かうか
シリコンバレーのベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者ベン・ホロウィッツ(もうひとりはMosaicを開発したマーク・アンドリーセン)による、ラウドクラウド、オプスウェアの経営、上場、売却などの経験から得た教訓が記された本。様々な大波が繰り返し押し寄せる企業経営の読み物としては、「PIXAR 〈ピクサー〉 世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話」と似た雰囲気を感じました。
上の「ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか」と同じことを言っている箇所もあって、そういう部分はおそらく「普遍的な真理なんだろうな」と思いながら読み進めました。自分が気づいたのは以下の2点。
- 「ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか」の主題でもあるが、「ゼロからなにかをつくり」という表現が何度か出てくる。
- スタートアップが必ず目指さなければいけない目標として「ほかよりも10倍効率的な製品を生み出す」というのがある。「ゼロ・トゥ・ワン」にも「10倍優れた」「10倍の改善」という表現が出てくる。
本書の中で好きな一節を引用しておきます。マーク・アンドリーセンの言葉です。
「いいかベン、物事は一番黒くなったあと、必ず完全な真っ黒になるんだ」
HARD THINGS 答えがない難問と困難にきみはどう立ち向かうか
いろいろと応用が効くと思います。
その他、
人、製品、利益を大切にする──この順番で
HARD THINGS 答えがない難問と困難にきみはどう立ち向かうか
など、組織のマネージャーやリーダーにも、一度は目を通していただきたい内容でした。
ジェフ・ベゾス 果てなき野望
Amazon創業者、ジェフ・ベゾスの半生。
奇しくも昨日(7月5日)、Amazonの設立記念日にCEOを退任し取締役執行会長に就くジェフ・ベゾス。ギリギリのタイミングで読めました。
日本では2014年刊なので、7年前までのAmazonの姿であり、AWSくらいまでは記載があります。その後のAmazonも、本書の内容からするとさらに凄まじい進化を遂げているはずで、2014年から現在までの進化も見てみたい気はします。
「弾み車を回す」など、「ビジョナリー・カンパニー」の引用が多かった気がします。まぁ、「ビジョナリー・カンパニー」、読んでないんですけど。
Amazon創業の書籍をAmazonの電子書籍リーダーKindleで読むと、UNIXで開発されたC言語でUNIXを書き換えるような趣きの深さがあるかもしれません(自分はKindleで読みました)。
学びを結果に変えるアウトプット大全
精神科医である樺沢紫苑氏による、脳科学をバックボーンにしたさまざまなアウトプット術。
短めのトピックに分かれていて読みやすいのですが、それに甘えてなかなか読み進めることができなかった本でもあります。また、
アウトプットが終わるまで、次の本を読み始めるべきではない
学びを結果に変えるアウトプット大全
とあるのに、アウトプット(当記事のことです)を先延ばしにするなど、あまり実践できてなかったり。
とは言え、もっとアウトプットを意識した生活に変えていこうというモチベーションは出てきたので、この一点においても読んで良かったかなと思ってます。
「100-300-1000の法則」についてはこちらに書きました。
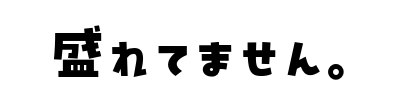
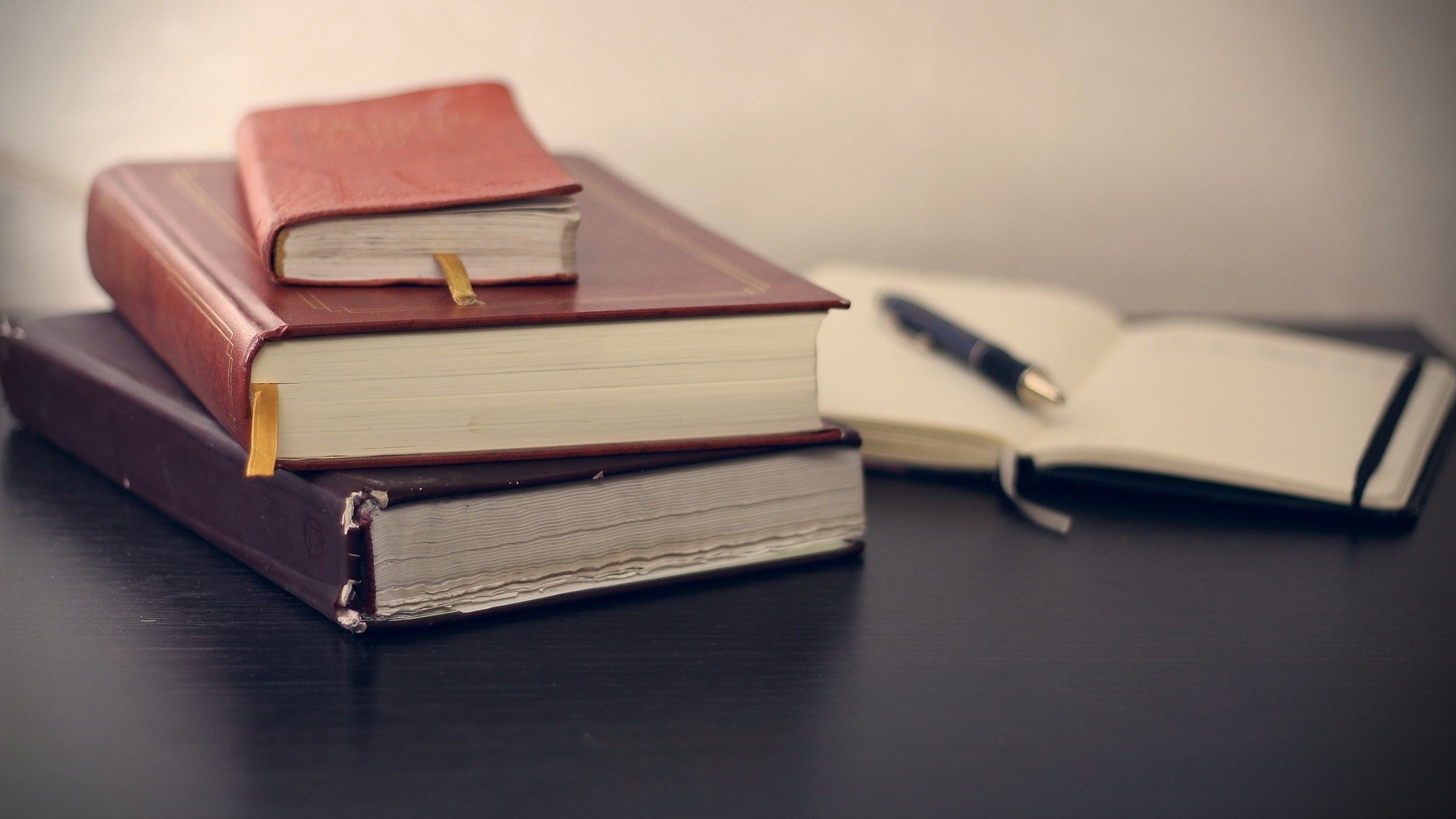










コメント